この記事では、
30代の共働き夫婦として双子を育てている我が家が、
子どもの成長に合わせてベビーサークルをどのように選び、
試行錯誤してきたかを実体験をもとにまとめています。
ベビーサークルは、
「これを買えば正解」というものがなく、
子どもの成長段階や家庭の環境、
その時々の生活の余裕によって最適な形が変わると感じています。
我が家も、最初から完成形を目指したわけではなく、
その時点で一番困っていたことをどう乗り切るかを基準に、
段階的に選び直してきました。
この記事では、
段ボールを使っていた時期から、
レンタルサークルを導入した時期、
現在のベビーゲート運用に至るまで、
実際に使って感じたことや判断の理由を記録しています。
同じように双子育児をしているご家庭や、
ベビーサークル選びに悩んでいる方が、
自分の家庭に合った選択を考える際の参考になれば幸いです。
我が家のベビーサークル遍歴:買い替え?追加?試行錯誤の記録
本記事は、双子育児をしている我が家が、
子どもの成長段階ごとに安全対策をどう考え、
どんな基準でベビーサークルを選んできたかの記録です。
ベビーサークルは「これを買えば正解」というものがなく、
子どもの成長 × 家の環境 × 親の余裕で最適解が変わると感じています。
我が家も、最初から完成形を目指したわけではなく、
「今しんどいところを、どう乗り切るか」を基準に段階的に選んできました。
①段ボール&プレイマット期
最初に囲いとして使っていたのは、家にあった段ボール。
双子分のオムツや備蓄水の箱を再利用し、とりあえず動ける範囲を制限する目的でした。
わが家の11畳間取り
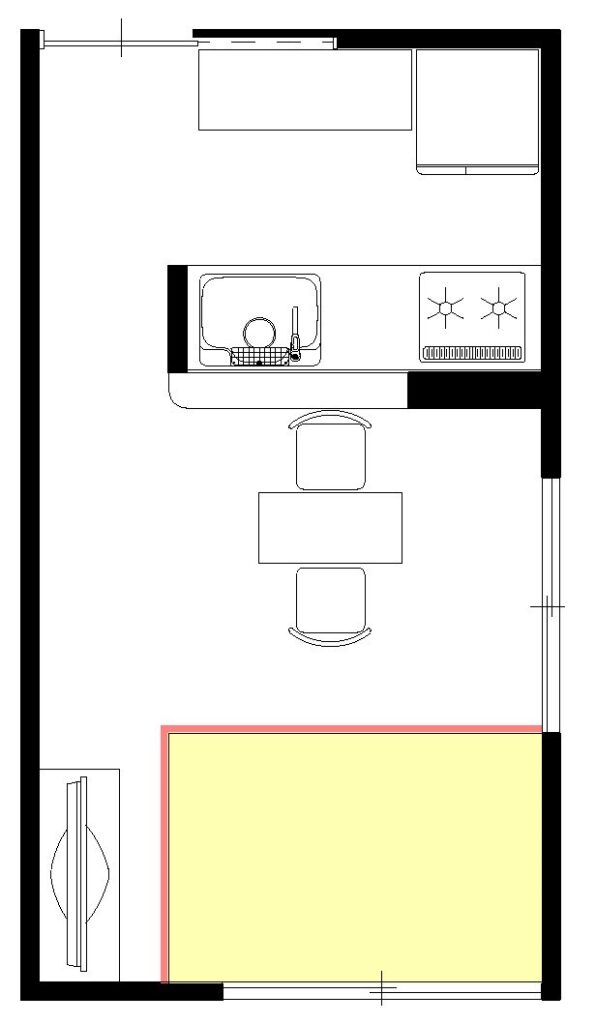
生活の変化(Before / After)
- Before
- 寝返り・ずりばいでどこまでも移動
- 頭をぶつけないか常に目が離せない
- 寝返り・ずりばいでどこまでも移動
- After
- 「ここにいれば大丈夫」という最低限の安心感
- 親の視線と神経の消耗が少し減る
- 「ここにいれば大丈夫」という最低限の安心感
同時に、それまで使っていたジョイントマットから、厚手のプレイマットに切り替えました。
ジョイントマットで感じた限界
- クッション性が足りず、転倒が心配
- 隙間にゴミやホコリが溜まる
- 掃除の手間が地味にストレス
- 端をかじられる(地味に困る)
プレイマットを選んだ理由
- 厚みがあり、転倒時の衝撃が和らぐ
- 折りたたみでき、掃除・移動が楽
- シームレス構造で液体が染み込みにくい
実際に使ってみて、「床環境が整うだけで育児の安心感が全然違う」と感じました。
ベビーサークル以前に、まず床を整えるのは多くの家庭におすすめできるポイントです。


②オムツ&備蓄水段ボール期(動きが活発に)
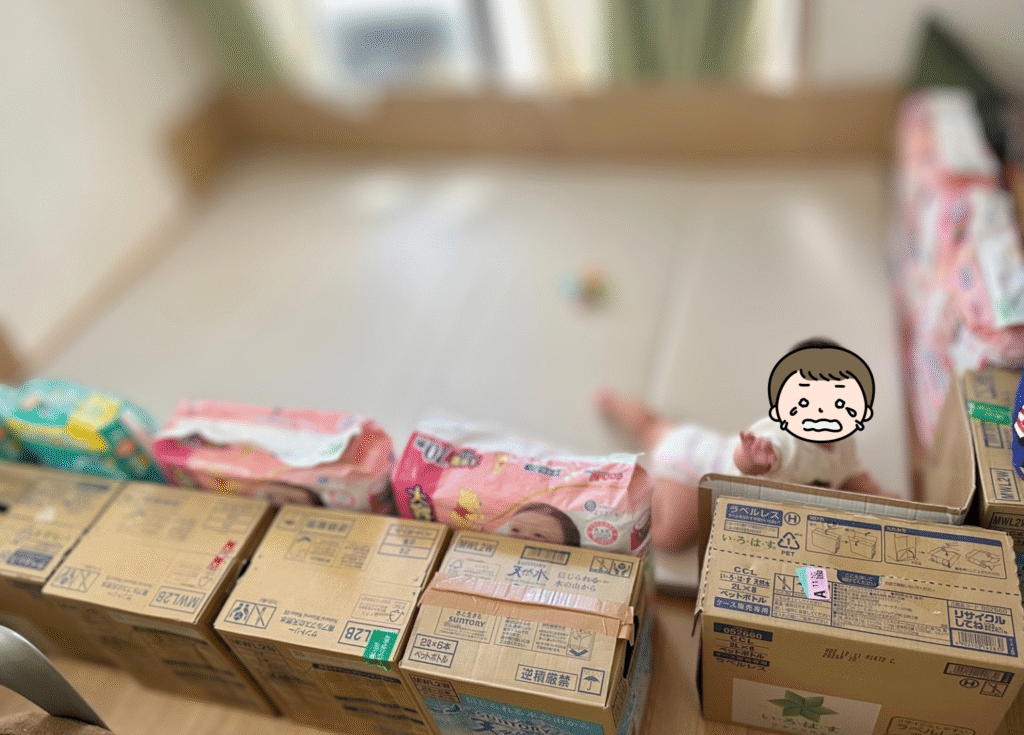
成長とともに、普通の段ボールでは簡単によじ登るようになりました。
そこで使ったのが、重さのある備蓄水の段ボールです。
工夫した点
- 重さでズレにくくする
- 角には未開封のオムツを置き、クッション代わりに
完璧ではありませんが、「今すぐ買わないと無理」という状況を一時的に回避できました。

③サークルレンタル期(生後8ヶ月頃〜)
それでも限界を感じ、生後8ヶ月ごろに本格的なベビーサークルを導入しました。
選んだのは
ナイスベビーでレンタルできる「日本育児 木製パーテーション」です。
※特定の商品を勧める目的ではなく、当時の我が家の選択例です。
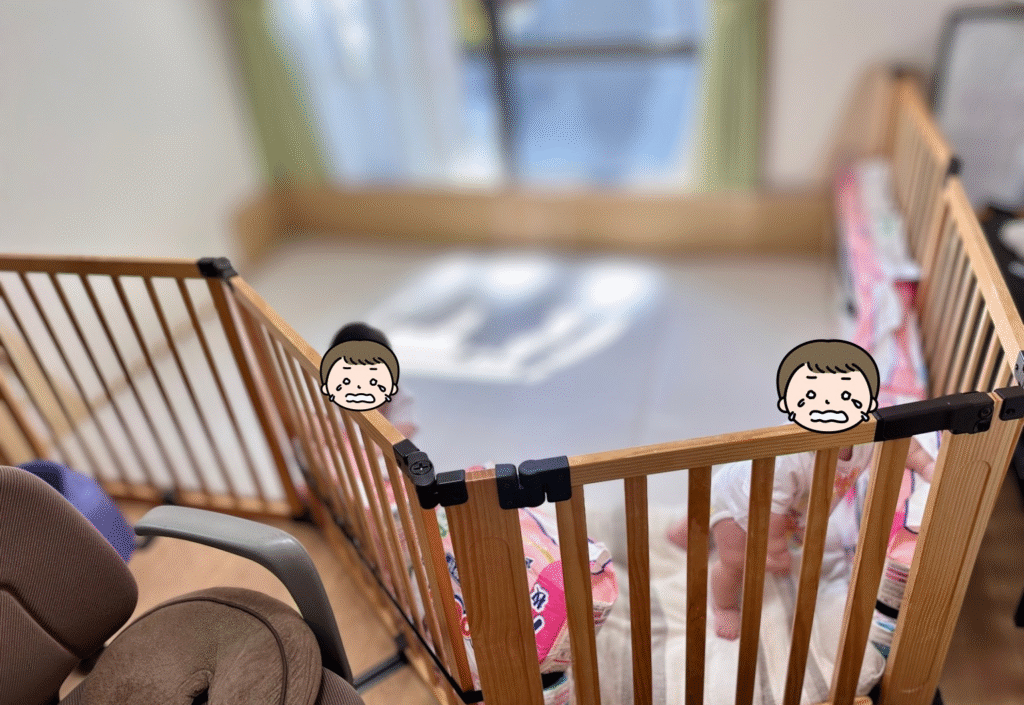
レンタルを選んだ理由
- ベビー用品は使用期間が短い
- 使わなくなった後の保管・処分が大変
- 必要な期間だけ使えるのは精神的に楽
このパーテーションは「子どもを囲う」だけでなく、
部屋をゾーン分けできる点が我が家には合っていました。
生活の変化
- 子どもゾーン/親ゾーンが明確に
- 料理・家事中のヒヤリが激減
- 「見守りながら別の作業」が可能に
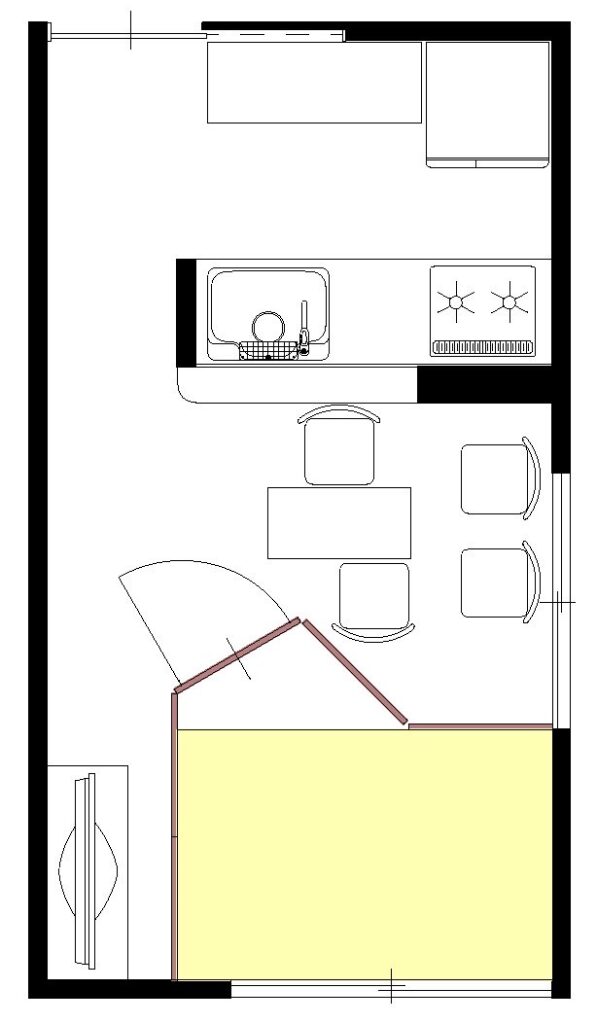

成長に合わせて形を変えられるのも助かり、
最終的には「子どもを囲う」より「触ってほしくない物を囲う」使い方に変化しました。
ただ、2歳前後になると力が強くなり、安全面のバランスが変わってきます。
我が家ではテレビを手放す決断をし、サークルも返却しました。
レンタル期間は約18ヶ月。
コスト面だけ見ると購入より高く感じるかもしれませんが、
使い終わった後のストレスがない点を含めると、満足度は高かったです。
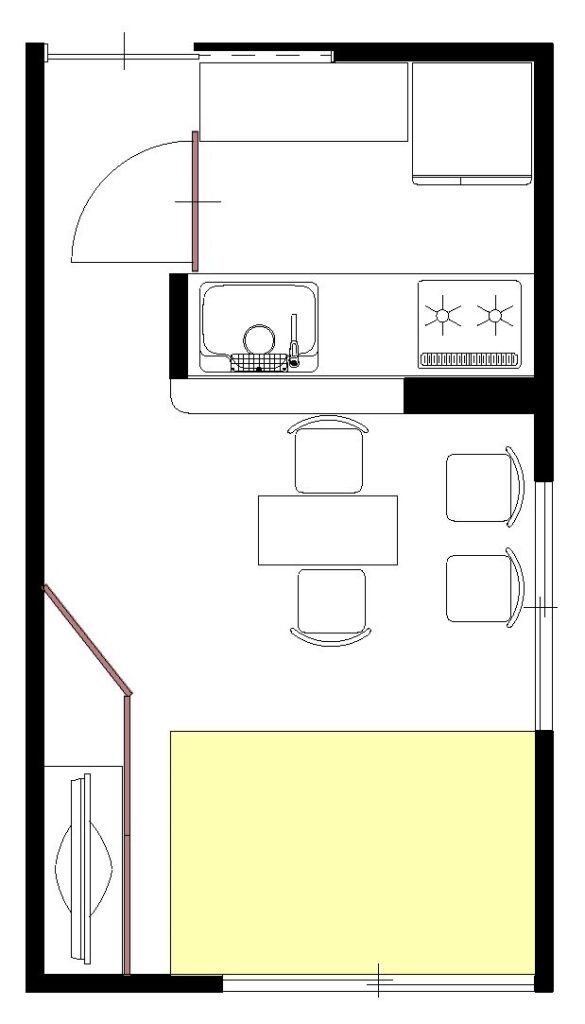

④現在:キッチンにベビーゲートのみ

現在は、キッチンの入口にのみベビーゲートを設置しています。
2歳5ヶ月になった今も現役です。
「危険な場所に近づかないことを教える」のは大切ですが、
双子育児では一瞬目を離した隙に何か起こるのが現実。
我が家では、
安全対策は仕組みで、教育は余裕のあるときに
という考え方を大切にしています。
まとめ:ベビーサークルは「家庭ごとの最適解」でいい
ベビーサークルを検討する際は、
- サークル型か、パーテーション型か
- 成長に合わせて形を変えられるか
- 最終的に「なくても安全な部屋」を目指せるか
こうした視点で考えると、後悔しにくくなると感じています。
我が家は双子育児ということもあり、
親の心の平穏を保つための道具として、サークル導入は本当に助けられました。
必要な時期だけ、無理のない形で取り入れる。
それで十分だと思います。うにお部屋作りをしようか悩んでいる方の参考になれば幸いです。



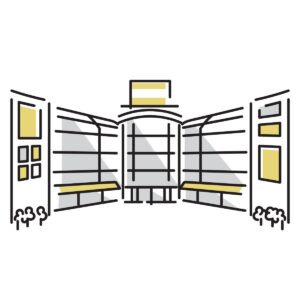





コメント